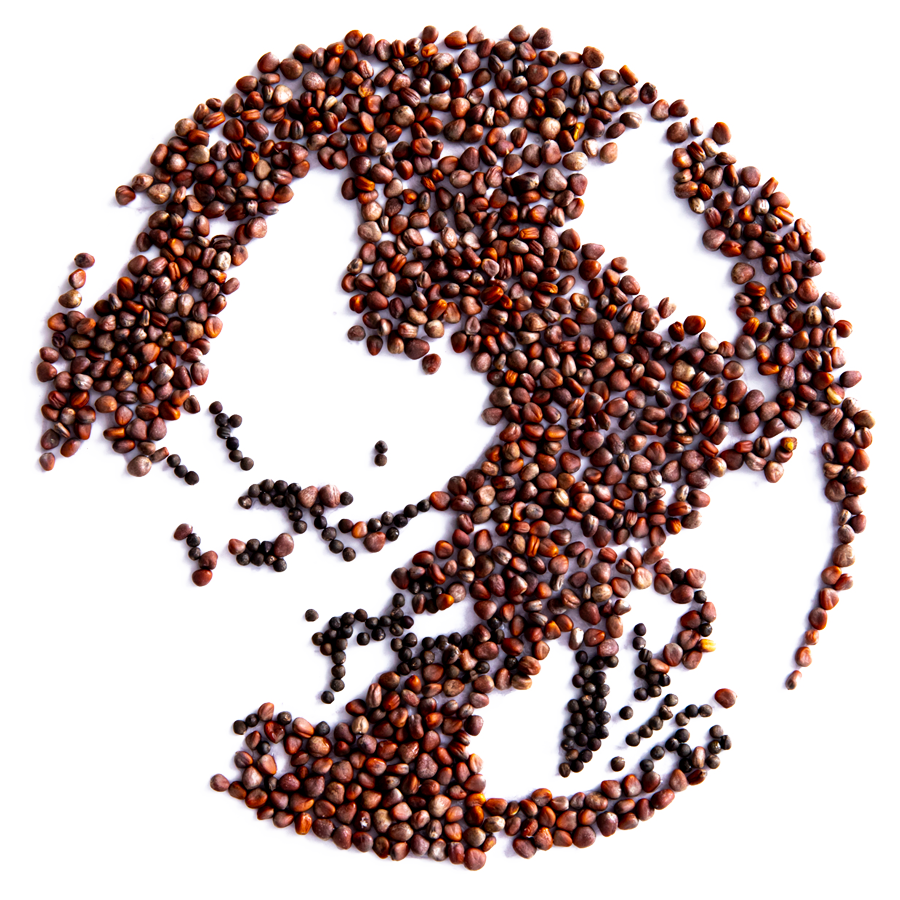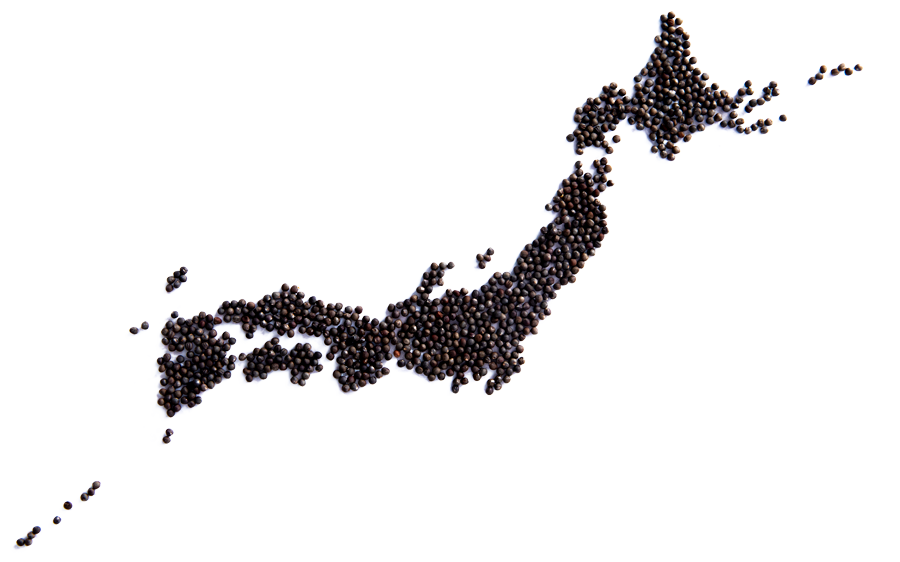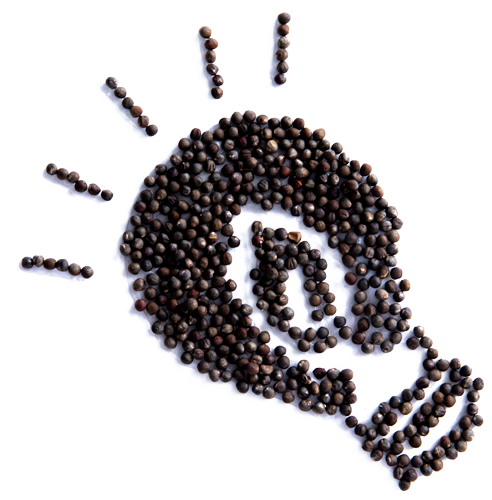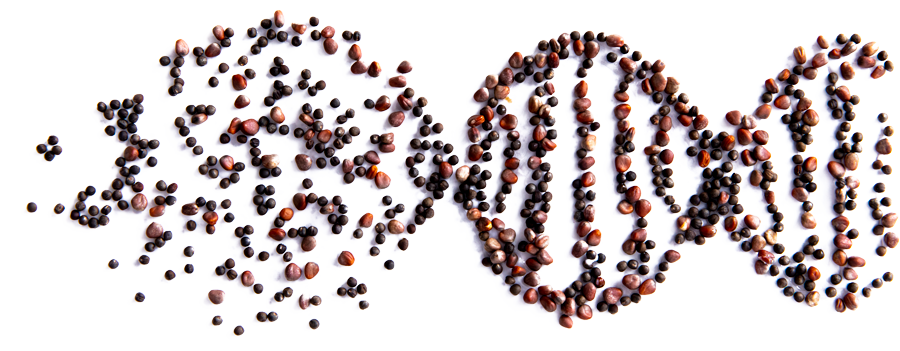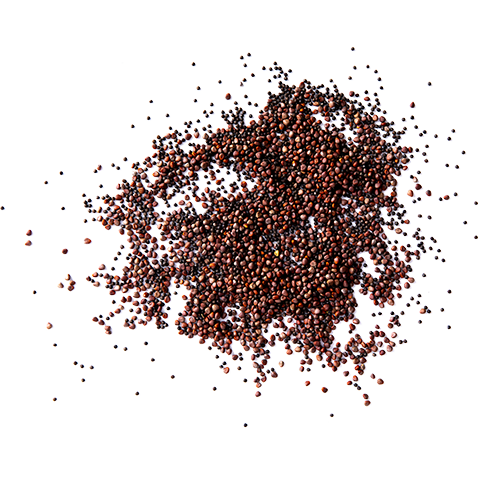皆さんが普段食べている野菜は、実は、数十年前は全く別物でした。たとえば、今でこそスラっと一直線でみずみずしいのが常識の大根は、昔は二股になっていたり、かじると中身がスカスカだったり。そんな状態を変えるために、何十年もタネと向き合い、野菜の常識を変えてきたのが私たちタキイ種苗です。では、タネは、どんな進化を遂げたのでしょうか。その挑戦における困難、喜びなどを知り尽くした六角が赤裸々に話します。

-
六角 啓一
1989年に研究職として入社。
栄養や成分などの観点から品種を開発するという新しい概念をタキイ種苗に導入した。ファイトリッチや桃太郎シリーズなど、会社を代表する多種多様な品種の開発に携わる。
生産者も、消費者も満足するタネを創り出す。
Mission
F1品種が誕生した1940年代、全国各地では“在来種”と呼ばれる野菜がつくられていました。そのなかで、生産者の皆さんから「収穫量を増やしたい」「もっとおいしい野菜をつくりたい」「栽培や収穫で、体への負担を少しでも減らしたい」といった声が挙がるようになりました。それらの要望に応えるため、タキイ種苗はどんな取り組みを行なったのでしょうか。
Action
まず最初に“長岡交配”のことをお話ししましょう。1940年代、タキイ種苗の研究農場は京都府乙訓新神足村、現在の長岡京市にありました。ここでは「もっと品質の高い野菜をつくろう」と、研究者がさまざまな交配を繰り返しており、研究農場のあった地域が当時から“長岡”という別名で呼ばれていたこともあって、ここで生まれた品種は「長岡交配」と呼称されることになったのです。この農場から生まれたのが、キュウリ“長型節成”“半白節成”、世界初の自家不和合成利用によるアブラナ科野菜の“一号甘藍”など。これらは“F1品種”と呼ばれ、病気に強く、気候の変動を受けにくく、形状の揃いやバラつきが少ない、収穫時期が統一できるなどさまざまなメリットを持たせることができました。たとえば、F1品種でロングセラーとなった大根“耐病総太り”は、それまでに栽培されていたものと比べて、地上に顔を出しているので収穫しやすい、中身もぎっしり詰まっており、品質にバラツキが少ない、そして、どれも一直線で大きさが統一されているため、輸送時の負担も少ないといった特徴がありました。これらの理由から、F1品種は生産者の方に大変喜んでいただくことができたのです。
そして、1900年代中盤を過ぎると世の中にスーパーマーケットなどが登場します。生活スタイルの変化に伴って、野菜も選びやすさ、輸送性がある、日持ちがする、安定供給できることなどがより重宝されるようになりました。それと同時に消費者も、野菜にこれまでよりももっと“おいしさ”を求めるように。生産のしやすさに加えて、おいしさも追求してつくられていたF1品種は、生産者、消費者のニーズとマッチし、市場を席巻していったのです。
では、F1品種とそれ以前のタネは、何が違うのでしょうか?簡単に言いますと、背が高い・低い、病気に強い・弱い、みずみずしい・パサパサなどの個体差が大きく、雑駁なのが以前のタネです。しかし、F1品種は品種特性が遺伝子レベルで揃っています。そのため、大きさ、味、強さなどで均一化するのです。のです。新しい品種を一つ作り上げるのには平均10年間を要します。タキイ種苗で脈々と受け継がれてきた粘り強さが、F1品種の創造を成功させたといえるでしょう。そして、この粘り強く、成功するまで諦めないという精神が、機能性成分に着目して開発された野菜のブランド“ファイトリッチ”の誕生に結びついていく、というわけです。

タネで、未来の社会問題を解決せよ。
Mission
おいしさ、安定供給、収穫量のアップを実現したタキイ種苗のF1品種は、農家→スーパーマーケット→消費者で構成されるバリューチェーンにガッチリはまり、進化を支える形でシェアを拡大していきました。しかし、1980年から1990年代に掛けて、タキイ種苗は社会の新たな問題を感じつつありました。その問題とは。そして、解決方法とは。
Action
私たちは、品種の研究を始める前、必ず未来をイメージするようにしています。先ほどもお伝えしましたが、一つの品種をつくるのに10年以上掛かるため、完成したときには世の中が大きく変わっている可能性があるのです。ファイトリッチの研究を始めたのは1990年代半ば。そのときから、私たちは高齢化社会が来ることを予測していました。そうなれば、体にやさしくて健康長寿に貢献できるが、開発において外せないテーマとなってきます。もう一つ予測していたのは、野菜が今よりも食べられなくなっている社会です。1986年以来、野菜の消費量が徐々に減少していることを示すデータもあったため、その現象になんとか歯止めを掛けたいという想いがありました。そのため、これまでとは視点を変え、機能性成分に着目した開発に取り掛かったのです。たとえば、緑色の野菜には抗酸化作用を持つ「ルテイン」という栄養分が多く含まれます。また、人参はカロテンの含有量が非常に多く含まれており、以前から私は「これらの成分をアピールしたら、野菜が体にいい食物であることがもっと消費者にわかりやすく伝わるのでは」と考えていました。そんな想いを実現するためのチャンスが、ファイトリッチの研究、機能性野菜の品種開発でもあったのです。 機能性プロジェクトは私がリーダーとなり品目ごとに担当者を決め、6名のメンバーでスタートしました。 決して大きなものではなく、会社の隅っこで細々と始まったプロジェクト、という感じでしたね。最初は薬草レベルまで成分を高めるというのはどうかという計画も出ました。しかしそれでは価格帯も変わってしまい、日常生活からかけ離れてしまう。そして、何よりもスーパーマーケットではなく薬局やドラッグストアで販売することとなります。そこで、「おいしい野菜、というポイントは守ろう」という結論になりました。このように、研究も紆余曲折の連続です。しかし、普段はそういう回り道が辛く感じるのですが、なぜか回り道すらおもしろかったことを覚えています。研究過程でお蔵入りになった品種も少なくありません。個人的には“おいしい紫の人参”をぜひ商品化したかった。紫色の天然色素にはアントシアニンという目に良い成分がたくさん含まれており、かつ、食べてもおいしかったんです。国の研究者と協働で動物実験を行った結果、体に良いこともわかり、試作段階まで漕ぎ着けたのですが、タネがどうしても採りにくく、商品化を断念したのです。もし、紫の人参が商品化していたら“人参=オレンジ”という常識が覆されていたかもしれませんね。

会社を動かし、ファイトリッチを社会に広めよ。
Mission
会社の片隅でスタートしたファイトリッチの研究は、決して順風満帆ではなく、数多くの苦難がありました。では、ファイトリッチが世に出るまで、どのような困難が待っていたのでしょうか。
Action
今でも鮮明に覚えているのが、育種目標検討会でファイトリッチの説明を初めて行った時です。育種目標検討会は年に1回行われる役員へ品種開発の目標をプレゼンする重要な場です。私たちは機能性成分の重要性や将来性を存分にアピールしたのですが、今までにないコンセプトでイメージし難いこともあり、全面的に今すぐに大きく投資するといった反応ではありませんでした。役員からオブラートに包んで「六角くん、これ売れるかいな?」と言われたのですが、役員の表情からは「残念だが、当分は売れない。時間がかかる」と確信していることが伺えました。しかし、その気持ちも理解できたんです。なにしろ、機能性成分に着目した品種の研究はタキイ種苗のなかでも初めてのこと。加えて、当時の社会では機能性成分の表示も存在しておらず、重要性も浸透していませんでした。ただし、役員へ将来への期待感を植え付けることができたとの実感は感じました。
まずは会社に、いかに魅力を理解してもらうか。そして、役員、営業、生産、すべての部署を巻き込んで全社的な取り組みにしてもらうか。考えた結果、研究を続けて、成果を出し続けるしかないと思い、10年以上研究を続けて社内へアピールを続けました。プロジェクトのメンバーへは時間が掛かっても良いから着実に成果を積み重ねて行こうと声を掛けて研究を続けました。時折、中途半端な妥協をしようと心が折れそうになりましたが、当時の上司が一番の応援者で強く背中を押してくれたことで何とか踏ん張ることができました。その中で少しずつ目に見えた成果が出始め、社内にも多くの理解者が増えていき、やっと手応えをつかんだのが、2005年、創業170周年の際に開催したお客さま向けの研修会です。プロトタイプのファイトリッチ試食会を開き、お客様から好評をいただいたのです。「これはいけるかもしれない」と光明が見えてきた瞬間でしたね。
そして5年後の2010年、ファイトリッチシリーズとして数種類の野菜が正式に発売されました。世の中では超高齢化社会が叫ばれており、消費者のあいだで健康志向が強まると同時に、食品に特定保健用食品(特保)を求める声も大きくなっていました。まさに、1990年代に私たちが描いたどおりの未来です。そこから、2017年からは発売する品種が17種類にまで増えていきました。 このファイトリッチシリーズ、私も家庭菜園で栽培しているんです。収穫したものを隣の家に住むおばあちゃんにプレゼントするのですが、いつも「ありがとう!」と大喜びされます。そりゃそうです。私が食べても、こんなにおいしい野菜はないと実感していますから。ファイトリッチを食べるたびにこう思います。「10年以上、折れず、腐らず、頑張ってきたかいがあった」と。