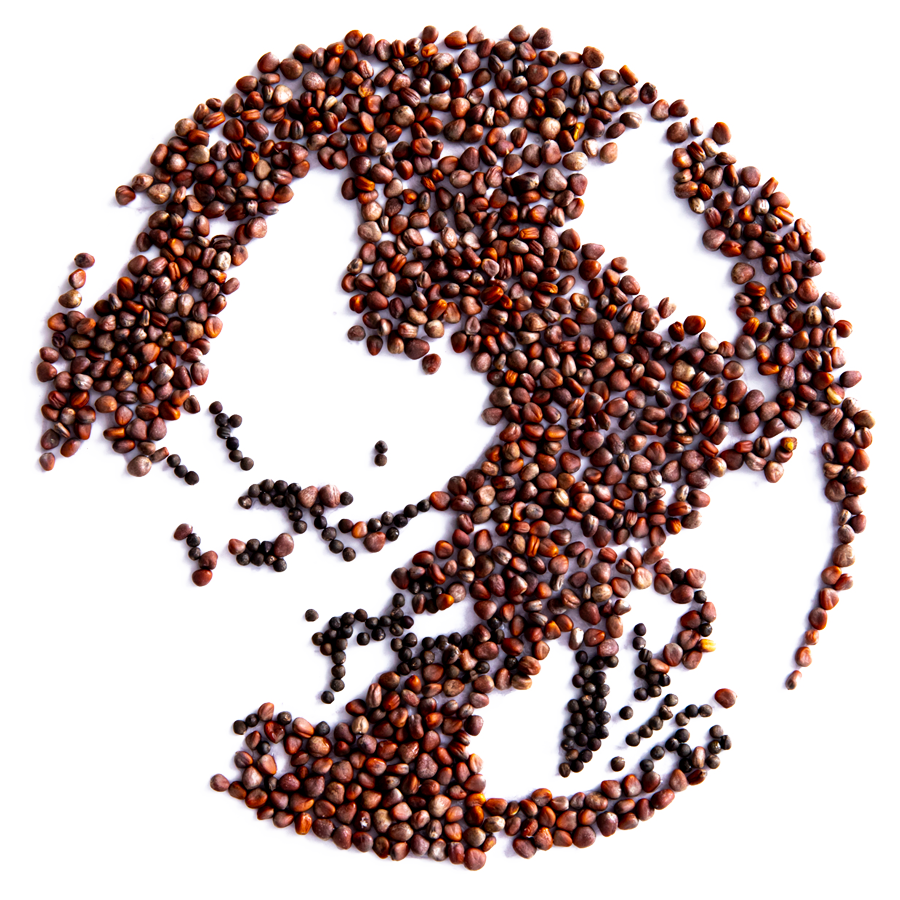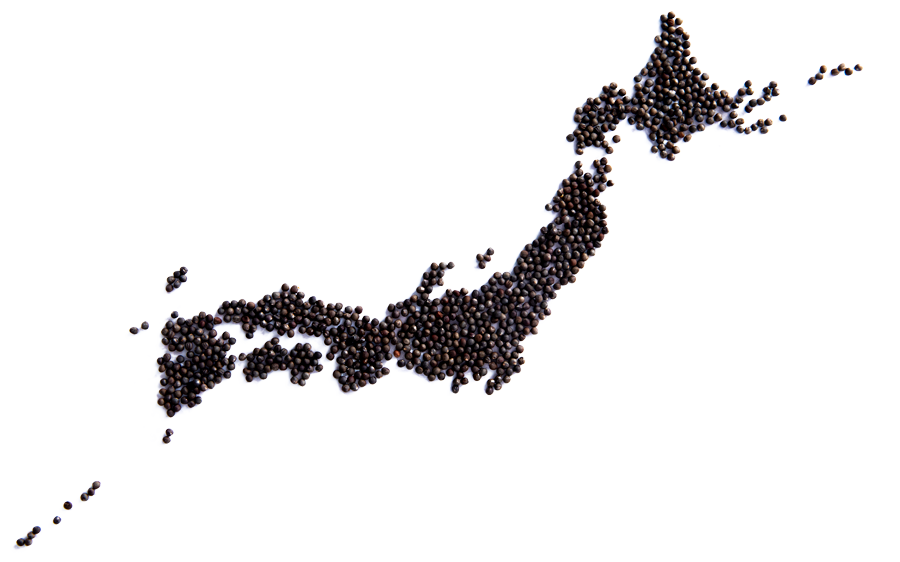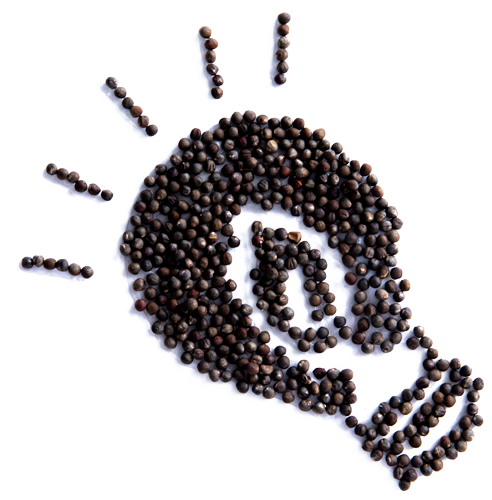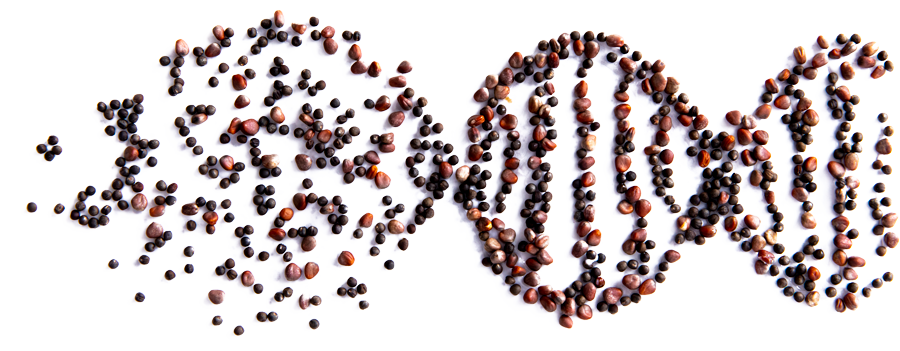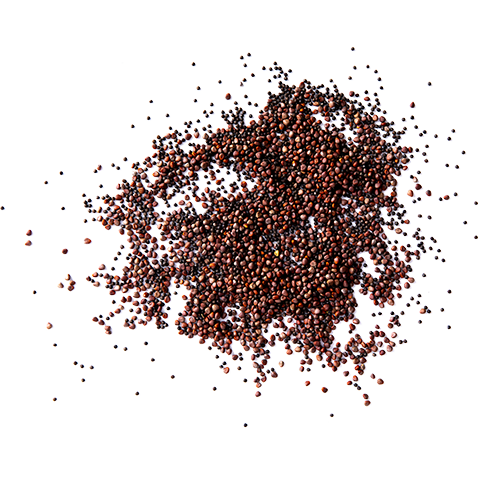COLUMN
タキイ種苗が日本、そして世界に誇る代表的品種“桃太郎トマト”。鮮やかな赤の実は、ガブっとかじると絶妙な甘さと酸味が口のなかに広がり、食べた人の心をグッと惹きつけます。ほとんどの野菜が「ピーマン」「ダイコン」といった品目名で販売されていますが、「桃太郎トマト」という品種名で店頭に並ぶようになっています。ここまで愛される桃太郎トマトが誕生したルーツを探ります。
桃太郎の先祖は、嫌われ者だった。
トマトの原生種は“パルビフローラム”という植物。青々とした小さな実が特徴で、人が食べると痺れを起こし、とても食用には向かないものでした。そこから何百年もの時を経て、紫外線などから身を守るために、青々とした実の色はどんどん変わっていったのです。そのなかで偶発的に生まれたのが、現在一般的な赤い色のトマト。不思議なことに、色が変わるにつれ、人に有害な成分が除去されて、食べても体の変調を訴える人はいなくなりました。以来、トマトは、世界中にどんどん広がっていったのです。

一度は届いた恋が、届かなくなった。
そして日本にやってきたトマトは、たくさんの人に受け入れられ、愛され、暮らしのなかに浸透していきました。しかし、1960年代トマトに大きな危機が訪れます。高度経済成長期に突入したことで、都市化が進み、トマトの栽培は郊外で行われるようになったのです。結果、栽培地から販売店に並ぶまでには、多くの時間を要することに。そのため、熟した状態で出荷すると輸送中に鮮度が落ちたり、トラックが揺れる衝撃に耐えられず形が崩れてしまいます。全国の生産者は、仕方なく熟する前の段階から出荷することにしました。すると「トマトの味が落ちた」と、そっぽを向く人が増えたのです。

桃太郎は、日本とアメリカのハーフだった。
トマトに逆風が吹くなか、一人の男が立ち上がりました。当時、タキイ種苗のブリーダーに従事していた住田です。「輸送しても崩れずに、一番おいしい状態で消費者のもとに届くトマトを作らなくては」。住田は当時日本で最も食べられていた“愛知ファースト”という品種をベースに、世界中のトマトを交配し、これからの時代に愛されるトマトづくりに挑み始めました。そして、取り組み始めてから6年。アメリカの“フロリダMH-1”という、従来の3倍もの固さを持つトマトと交配した結果、望みの固さを実現することに成功したのです。しかし、決して満足のいく“おいしい味”にはなりませんでした。悔しさを住田が襲います。

科学的根拠から生まれた、桃太郎。
住田は、トマトが持つおいしさの理由を徹底的に調べました。その結果、判明したのが“トマトの黄金比”。グルタミン酸1:酸4:糖40という比率が実現できたら、誰もが「おいしい!」と惚れ込むトマトができるということがわかったのです。 そこから研究は急ピッチで進みました。愛知ファーストとフロリダMH-1を交配したトマトは、糖とグルタミン酸が少ない。それならば、と、普通のトマトの2倍におよぶ糖度を持つミニトマトと、グルタミン酸が多めのトマトを交配しました。その結果、住田の開発したトマトは申し分ない味に。そして1983年、日本人が「一番おいしい」と思える“桃太郎トマト”が誕生したのです。
仲間を増やし、桃太郎は世界中の人気者に。
1985年に発売されて以来、桃太郎トマトは世の中を席巻しました。いつどこで購入しても、求めていた甘さと酸味を変わらず楽しめる。瞬く間にシェアは広がり、国内におけるトマトの全消費量で、当時のシェアは70〜80%ほどを占めるまでになったのです。桃太郎トマト自体も、継続的な品種改良でラインナップが増加し、今では20種類以上が流通しています。そのなかには、シス型リコピンを多く含む“桃太郎ゴールド”という橙黄色の品種も。こちらも消費者から好評を博しています。桃太郎の仲間はどんどん増えているのです。嫌われ者から一転して、世界中の人気者になったトマト。これからも進化への旅はまだまだ続きます。